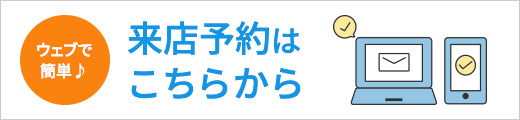- 補聴器

補聴器を長く愛用している方のなかには、「最近、機能が少し衰えてきた気がする」「そろそろ限界かもしれない」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
快適な生活を送るためには、補聴器を適切なタイミングで買い替えることが大切です。今回は、補聴器の寿命や買い替えを検討すべきタイミングについて解説します。
補聴器の一般的な寿命

補聴器の買い替えを検討する目安として、機器の寿命があげられます。寿命が近い補聴器は、ある日突然、異常が起きる可能性があります。
聞こえに影響が出る前に、ベストなタイミングで補聴器を買い替えるためにも、製品の寿命はある程度把握しておく必要があります。
まずは、補聴器の一般的な寿命や買い替えの頻度、メーカー各社が設定する保証期間について解説します。
補聴器の耐用年数
一般的な補聴器の耐用年数は、約5年です。5年を基準とする理由は、テクノエイド協会の「補装具費支給事務ガイドブック」への記載があげられます。ガイドに沿って、耐用年数を5年に設定しているメーカーもあります。
ただし、耐用年数5年はあくまで目安です。ガイドブックには、耐用年数が経過した後も性能が十分に保たれている場合は、補聴器の再支給が認められないことが記載されています。反対に、5年未満の使用期間でも、補聴器の状態によっては寿命と認められる場合もあります。
出典:公益財団テクノエイド協会「補装具費支給事務ガイドブック(平成 30 年度 告示改正対応版)」
買い替えの頻度
補聴器を買い替える頻度は、約4年の方が多い傾向にあります。
本補聴器工業会が2022年に発表した資料によれば、年数別に見ると1~3年で買い替えている方は48%で、4~6年の方は31%でした。約半数は3年以内で、残りの約半数は4年以上経ってから補聴器を買い替えていました。
なかには、前述の耐用年数5年を超えて、長期間使用し続けている方もいます。
出典:一般社団法人日本補聴器工業会「Japan Trak2022調査結果」
補聴器の保証期間
補聴器の保証期間は、メーカーによって多少異なりつつも、概ね1~3年の保証期間が設けられています。メーカー保証は、2年が一般的です。一方、総合支援法で支給される補聴器は1年間の保証期間があり、修理時は補助金が支給される仕組みです。
注意点は、保証期間はあくまで通常使用時、不具合や故障などが生じた場合にのみ適用されることです。過失による破損や紛失などは、保証対象外となります。
補聴器の買い替えをするタイミング

ここでは、実際にいつ新調するべきか、補聴器の買い替えを検討するべきタイミングを解説します。次のようなトラブルや異常が生じたときは、補聴器の買い替えを考えてみましょう。
下記の事情で、補聴器の修理が困難な場合は、買い替えを検討しても良いタイミングです。
・メーカー保証が切れており有償修理となる
・部品がなく修理自体が不可なとき
・著しい破損で修理不可能なとき
など
前述の通り、多くのメーカーでは補聴器の保証が2年程度です。保証切れの補聴器を修理する場合は、簡単な作業内容であっても有償となることがほとんどです。
購入から何年も経っている補聴器の場合、そもそも部品自体が生産終了して入手できない可能性があります。互換性のある部品が見つからなければ、修理自体できないからです。また、仮に保証期間内であっても、破損状況によっては修理できない可能性もあります。
聞こえ方に変化があるとき
補聴器の聞こえ方に変化が生じた場合は、修理や買い替えが必要です。全体的に聞こえにくくなる場合もあれば、片耳だけ聞こえなかったり、特定の音だけ聞こえなかったりすることもあります。聞こえ方が変わると、会話にも支障をきたしかねません。
また、長年愛用している方は、加齢による聴力低下が原因の場合もあります。聞こえ方が変わったと感じたら、改めて自分の聴力や使い方に合った補聴器への買い替えの検討も必要です。
生活に変化があるとき
生活環境が大きく変わったときも、補聴器の買い替えを検討するタイミングです。例えば、家の中での使用していた方が外でも頻繁に使用するようになった場合、補聴器のサポートを受けたい音が変わることがあります。
使用時間が長くなったときも、生活環境や使用シーンに合わせて補聴器の買い替えを検討しましょう。補聴器は、機種ごとに装着感や聞こえ方が異なるため、用途に合った製品を選ぶことが大切です。
補聴器に劣化がみられるとき
補聴器に下記のような劣化が出たときも、買い替えのタイミングです。
・ひび割れなど本体の劣化がある
・電池の持ちが悪くなった
・頻繁に故障するようになった
・音割れするようになった
など
上記のほかにも、違和感や使いにくさを覚えた場合は、修理のほかに補聴器の新調も視野に入れましょう。
古い機種を使い続けているとき
何年も前に購入した補聴器を使用している方は、聞こえにくいといった不満が出ることもあるのではないでしょうか。補聴器の機能は日々進歩しており、高い性能で使い勝手の良い機種が開発されています。使用している補聴器に不満が出始めた際も、買い替えのタイミングです。
新しい補聴器に買い替えれば、古い機種では聞こえなかった音も聞き取れたり、音が入りやすくなったり、利便性が向上します。
補聴器を長く愛用するためのポイント

大切な補聴器を少しでも長く愛用するためには、4つのポイントを意識することが大切です。
水や湿気に注意する
水分や湿気は、補聴器にとって大敵です。故障の原因となるため、汗や雨、結露で濡れないように注意しましょう。また、お風呂場に持ち込むことも避けるべきです。
使用後も水や湿気から守るために、必ず乾燥ケースに入れて保管します。補聴器を乾燥させることで、長持ちにつながります。万が一、補聴器が濡れたときは、すぐに水気を拭き取ってください。
高温と衝撃に注意する
補聴器は精密機器であり、衝撃や熱に弱い特徴があります。高温の場所に置いたり衝撃を与えたりすると、故障の原因となりかねません。補聴器を置く場所には、注意しましょう。
例えば、真夏の車内に置きっぱなしにしたり火のそばに置いたりすると、故障することがあります。外すときは、乾燥ケースに仕舞うように習慣づけしておくと、故障のみならず紛失の防止にもなります。
日々お手入れをする
補聴器は、毎日お手入れすることをおすすめします。装着していると耳垢やほこりが付着しやすいため、定期的に拭き取ってきれいな状態を保ちましょう。お手入れするときは、まず手を石鹸で洗い、清潔な状態で取り扱うことが大切です。
お手入れする場所は、ある程度広くほこりが付着しにくい安全な場所がおすすめです。清潔なテーブルの上なら、手が滑って落としても、ほこりが付着する心配はありません。
販売店で定期的なメンテナンスをする
日々のお手入れに加えて、販売店で定期的にメンテナンスを受けると、より長持ちします。自宅メンテナンスでは届かない細部も、専門知識のあるスタッフに見てもらうことで、異常を素早く見つけられるメリットもあります。
販売店でのメンテナンスは、1~3ヶ月に1回の頻度がおすすめです。少なくとも3ヶ月に1回はメンテナンスを受けるようにすると、買い替えのタイミングも相談できます。
定期的なメンテナンスの時期が来ていなくとも、気になる点があればすぐに販売店へ持ち込むことも大切です。
まとめ
補聴器の耐用年数は約5年であるものの、耐用年数が過ぎても必ずしも壊れるわけではありません。
一方で、補聴器は日々進化しており、新しい機種のほうが聞こえが良くなったり利便性に優れたりすることもあります。愛用している補聴器への不満や使用するときの環境なども考慮して、自分にベストなタイミングで買い替えを検討することが大切です。
補聴器の新調をお考えの方は、ぜひ10日間ご自宅で補聴器体験(無料)できるメガネのヨネザワへご相談ください。丁寧なカウンセリングを行い、お客様の「聞こえ」のお悩みに寄り添ったベストな補聴器をご提案いたします。