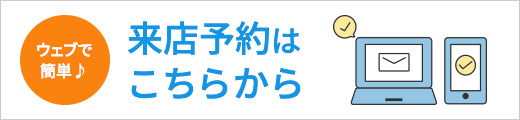- 補聴器

補聴器は適切にお手入れすれば、ある程度寿命を伸ばせます。定期的なメンテナンスをすることで、将来的なコストの節約にもつながります。
今回は、補聴器の適切なメンテナンス方法について解説します。
補聴器はメンテナンスで寿命が伸びる!

補聴器の一般的な寿命年数は約5年といわれており、年数が経つにつれて劣化が進んでパフォーマンスが低下していきます。劣化の原因はさまざまですが、主に部品の摩耗・汚れの蓄積・衝撃による損傷などが考えられます。
毎日耳に装着するものなのでどうしても傷や汚れが付きやすいですが、定期的にメンテナンスをすれば、清潔な状態をキープしつつ深い傷が付くのを予防できます。結果として補聴器の寿命が伸び、長く使えるようになります。
メンテナンスすることは、補聴器を長持ちさせるだけでなく、聞こえ方など補聴器本来の機能を十分に発揮させる面でも重要です。クリアな音をしっかり聞き取れることは、生活の質にも大きく影響します。
家族との会話や音楽などをしっかり楽しむためにも、補聴器の正しいメンテナンス方法を知って適切にお手入れしていきましょう。
毎日行う補聴器のメンテナンス

まずは、毎日行うメンテナンスを紹介します。
補聴器を使う前後に乾拭きする
精密機器である補聴器は水や湿気、汚れなどを嫌う製品です。耳の穴に入れていると汗や耳垢などが付いてしまうことがあり、放っておくと汚れが蓄積してしまいます。
そのため、補聴器を使用する前後は乾いた柔らかい布を使って汚れなどを拭き取るようにしましょう。
もし水や汗などで濡れてしまった場合は、放置せずにすぐに拭き取ることが大切です。
水で湿らせた布のほうが汚れが落ちやすいイメージがありますが、故障を防ぐためにも、補聴器を拭くときは必ず乾いた布を使ってください。
お手入れには綿棒などを使うほか、専用のお掃除ブラシなどもあるので、メンテナンス用に準備するのもおすすめです。
補聴器を乾燥用ケースで保管する
補聴器を使用しないときは電池ケースをしっかり開いておき、補聴器の乾燥用ケースに収納して保管しましょう。使い終わった後に専用ケースに収納することで、紛失防止にも役立ちます。
近年では、本体に撥水加工を施した補聴器も登場しており、湿気が原因で故障するケースが少なくなってきています。
ただ、補聴器が精密機器で湿気に弱いことには変わりありません。過信せず、十分に乾燥させておくことが重要です。
お風呂に入るときに外す方も多いと思いますが、湿度が高くなりやすい洗面所やお風呂場などに放置しないように注意しましょう。
補聴器の乾燥ケースには、乾燥剤を使うタイプと電気を使うタイプがあります。乾燥剤を使うタイプでは、シリカゲルの定期的な交換が必要です。時期が来たら確実に取り替え、しっかり乾燥できるように気を配っておきましょう。
都度行う補聴器のメンテナンス

毎日行うメンテナンスに加え、汚れが目立ったときや電池が減ってきたときなど、状況に応じて行うメンテナンスもあります。
ここでは、気が付いたときにその都度行うメンテナンスを紹介します。
掃除をする
補聴器は精密機械なので、ほこりや汚れに敏感です。本体の汚れが気になったときや、ほこりがついてしまったときは、その都度きれいに掃除しておきましょう。
特に、外出していて土や砂がついた手で補聴器に触ったり、砂ぼこりが立つような場所で使ったりしたときは、細かい汚れが補聴器についている可能性も否定できません。放置せずに、乾いた布やブラシなどで丁寧に払っておくと安心です。
補聴器の音が出る部分には穴が開いており、使っているうちに耳垢などが入り込んでしまうこともあります。綿棒や専用ブラシなどを使ってこまめに掃除をしておきましょう。
電池交換をする
電池の残量が少なくなってきたら、忘れずに電池交換を行いましょう。補聴器に使う電池の寿命は補聴器そのものや電池の種類によって違うので、販売店で確認しておくことをおすすめします。
電池がどのくらいもつかは使っている状況などにもよりますが、聞こえ方が気になるようなら、早めに電池交換しておくと安心です。
補聴器に入れる電池にはさまざまな種類があるので、今お使いの補聴器の電池の種類を確認してから購入してください。
電池の種類は、下記のように色分けして区別されています。
- 10A(PR536):黄色
- 312(PR41):茶色
- 13(PR48):オレンジ色
- 675(PR44):青色
また、補聴器の電池にはシールがついていますが、剥がした瞬間から電池の消耗が始まります。そのため、電池のシールは使う直前に剥がすと良いでしょう。
なお、シールを剥がしてからは、30秒~1分ほど待ってから使うと作動しやすいといわれています。
そのほか、電池を正しく使うことも重要です。上下を逆に入れたり、補聴器用ではなく時計やゲーム機用のボタン電池を使用したりなど、使い方を間違えると故障の原因になるので注意しましょう。
使い終わった電池を捨てるときは、セロハンテープを電池に貼って絶縁し、補聴器販売店に持ち込んで処分してもらいましょう。
精密点検・精密清掃を依頼する
補聴器は購入後もお手入れをしっかり続けていれば、本体を良い状態でキープしやすくなります。さらに、定期的に点検や清掃をしてもらうと、故障が防止でき、補聴器の寿命をより延ばすことができます。
可能であれば、1ヶ月に1度ぐらいの頻度で補聴器を購入した店舗に点検を依頼し、2年に1度くらいの頻度で補聴器を分解点検に出していただくことがおすすめです。
なお、点検の費用や申し込み方法は店舗によって違うので、補聴器を購入する時にアフターメンテナンスについて確認しておきましょう。
まとめ
補聴器のメンテナンスも含め、補聴器の購入などのご相談はメガネのヨネザワにお任せください。
メガネのヨネザワは、九州の各地域および山口・宮城県で180店舗を展開する視聴覚の専門店です。メガネ(眼鏡)やコンタクトレンズ、補聴器、福祉機器などの販売を手がけています。
聞こえの相談や補聴器の体験、メンテナンスや調整などに対応できる専門スタッフが常駐しているのが強みです。認定補聴器技能者も140名以上在籍しており、補聴器に関する最新の設備や、試聴機器も豊富に取りそろえています。
補聴器は毎日行うメンテナンスと、気が付いたときにその都度行うメンテナンスがあり、そこに専門店での点検も加えれば補聴器を長く快適に使用できます。メガネのヨネザワでも専門スタッフがお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。